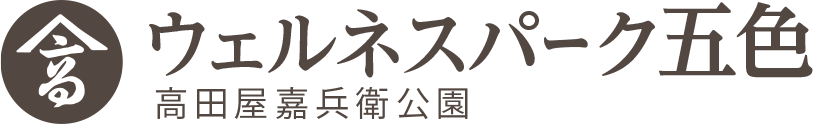名刀
10月4日は「日本刀の日」です。
とう(10)し(4)ょう【刀匠】の語呂合わせにちなんで全日本刀匠会が10月4日に
記念日を制定しております。
刀匠とは日本刀を作る職人ことです。
私は、たくさんのゲームやアニメをしたり見てきたのですが
その中で出てくる日本刀のかっこよさに魅入られたものです。
実は、淡路島には、名刀菊一文字を所蔵する神社があります。淡路島淡路市東浦にある松帆神社です。

名刀菊一文字は、昭和初期に発見されて、国の重要美術品に認定されています。松帆神社は、1399年に創建された八幡宮(八幡さん)である松帆神社は、古くは楠木正成公と深い由縁があり、名刀菊一文字は、遺愛の太刀といわれています。
名刀菊一文字は、鎌倉時代初期にあたる1207年から1211年の承元時代に作られた古刀です。現在では、松帆神社の社宝であり、国の重要美術品となっています。
当時、後鳥羽上皇が全国より名刀工を呼び集めて御番鍛冶として鍛刀させていました。名刀菊一文字は、御番鍛冶の筆頭であり、備前国の刀工の一派「福岡一文字」の祖である則宗の作と見られています。
菊一文字の名前は、則宗の作刀の腕が後鳥羽上皇に認められたために、菊の御紋を頂戴することになったことに由来します。菊の御紋の下に横一文字を足して彫ったことから菊一文字となりました。
古来より、「八幡宮(松帆神社の旧社名)に名刀あり」との口伝や噂などはあったそうですが、松帆神社の何処にあるのか、どんな名刀なのかは判然とせずに歳月だけが流れていきました。
昭和初期に、松帆神社の本殿奥の内陣からたまたま日本刀が発見されました。研磨すると見事な日本刀でした。1933年9月に日本刀の鑑定者であり鑑刀宗家の本阿弥光遜氏が鑑定をしました。
「在銘にしてかかる優れた出来栄えの日本刀にはここ数年接した事がない。七百有余年を経て、なを且つ生(うぶ)に等しい刀姿は余程手持ちが良かったこともあろうが、宝刀の宝刀たる所以でもある。かかる尊貴の御刀が出てきたからにはさぞかし由緒ある神社に相違ない」と激賞されました。
本阿弥光遜氏による鑑定結果は、「菊御作」であり「正真」との鑑定となりました。
当時の文部省の国宝保存課刀剣主査である本間順治博士からは「間違いなく菊一文字で、鞘(さや)・柄(つか)・鍔(つば)の拵えも刀身に劣らぬ世に珍しいもので、両々相まって重要美術品に認定する」と評価を受けています。
昭和10年5月20日付で松帆神社の名刀菊一文字は、国の重要美術品に認定されました。当時、突然の名刀菊一文字の発見から由来には様々な説が出されました。
名刀菊一文字は、有力大名でなければ入手不可能と言われるほど非常な希少であったこと、楠木正成公の家臣 吉川弥六の末裔 吉川家に「名刀菊一文字は落ち延びた家臣で廻し持ちして、領主を通じて八幡宮に奉納した」と口伝があったことが、歴史的な証拠となりました。
ただ、名刀菊一文字が松帆神社に辿り着くまでどのような経緯を辿ったのかを証明する資料が無かったことから、国の重要文化財でなく、重要美術品という位置づけになりました。
名刀菊一文字は建武の新政の立役者であった楠木正成公が恩賞として賜った太刀として、名刀菊一文字は楠木正成公の遺愛の太刀として伝えられるようになりました。
現在、松帆神社では、細心の注意を必要とする貴重な名刀菊一文字の管理を担うことから、10月第1週日曜日の例大祭(秋祭り)の日に限り宝物殿を開放して一般公開を行っています。
例大祭(秋祭り)の当日以外で名刀菊一文字の観覧はできません。代替として、社務所にて名刀菊一文字の関連資料を常設展示しております。

もうすぐ10月になりますので、日本刀が好きな方・見てみたい方はぜひ淡路島にお越しください。